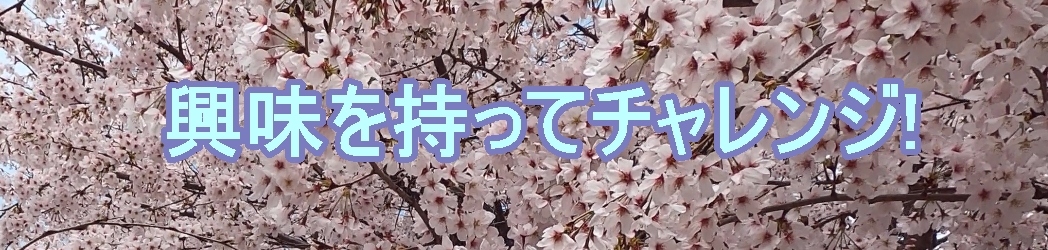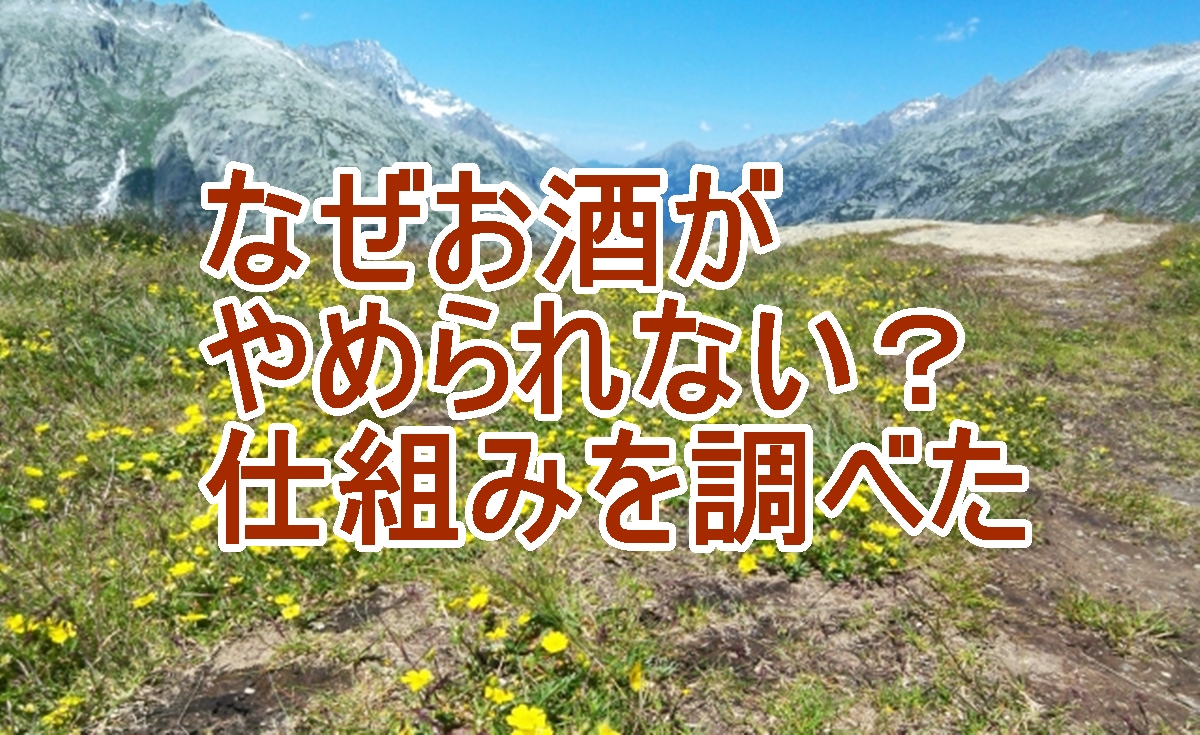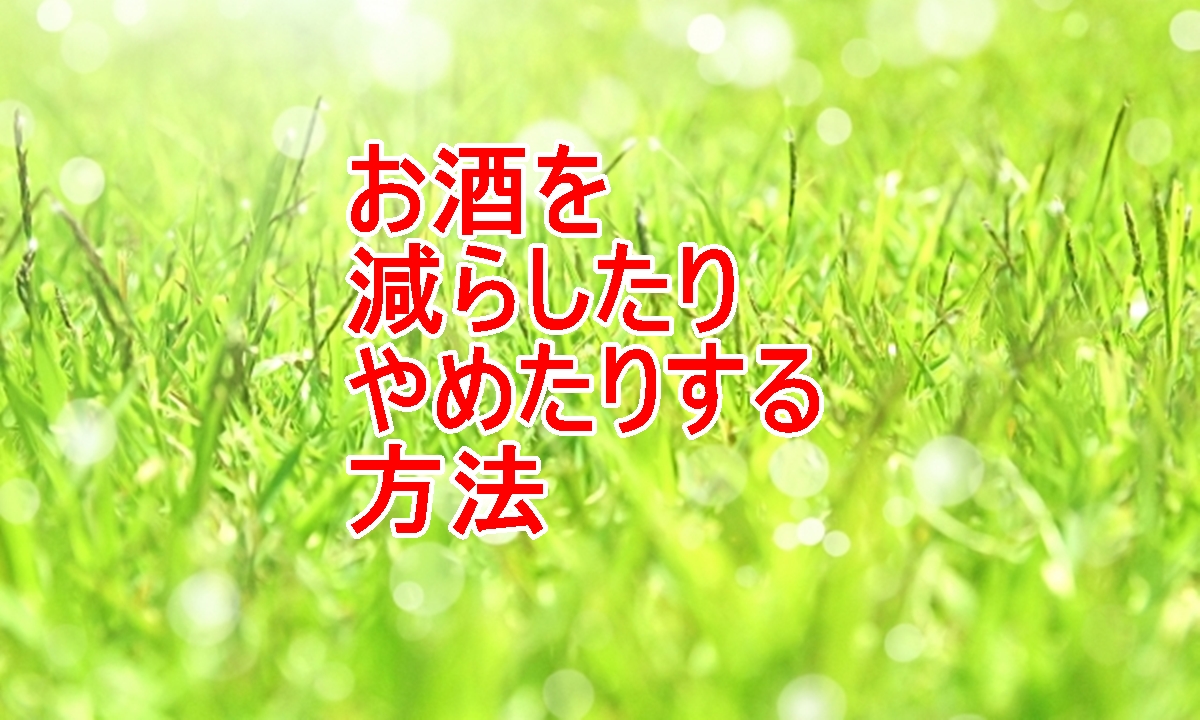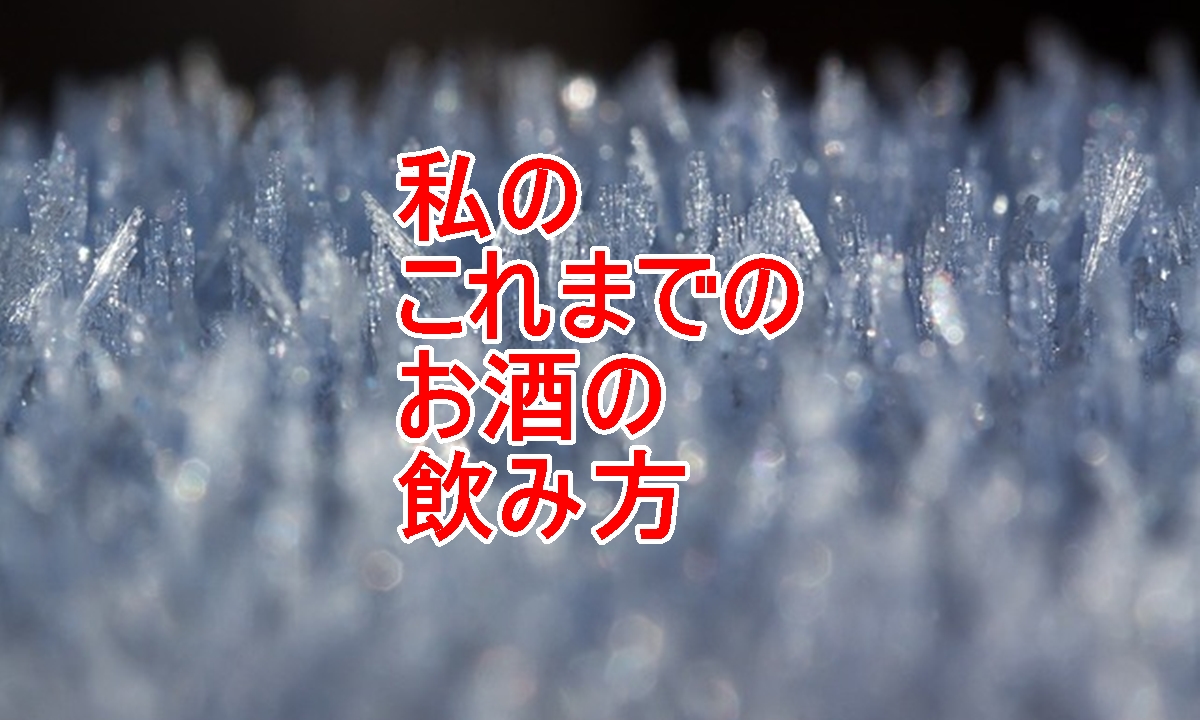はじめに:
60歳代になって痛風発作が繰り返し起こってとても困りました。発作は尿酸値が高いままでいると再発するので、尿酸値を下げるために飲酒をやめるのが即効性があります。ところがわたしにはお酒を飲むのをなかなかやめられません。なぜお酒がやめられないのか? ネットで調べると、どうやら脳の影響が大きく働いているようです。飲酒を長く続けるほどに脳がやめさせないよう働くようなんです。今回の記事は、ネットで収集した情報をわたしなりにまとめて整理してみました。
飲酒の習慣はやめられなくなります
お酒はたくさん飲み続ける期間があるといけません。お酒を断っても気が緩んでちょっとでも飲んでしまうとリセットされてしまいます。お酒を飲むのをやめたくてもやめられなくなる、これがお酒の持つ高いリスクです。
私も少しの間お酒をやめてはまた前よりも飲んでしまう、そういう経験を何度かして、やるせないです。なぜ、お酒(アルコール)を飲むのがやめられないのか?調べてみると、単に意志が弱いからというわけではありませんでした。以下、ネットの情報を引用していきます。
お酒がやめられないメカニズム
お酒がやめられなくなるのは、脳内物質のバランスが崩れた状態だという説を最初に紹介します。
たばこ、酒、甘いもの…からだによくないことがわかっているのに、どうしてもやめられない。これらのものに依存してしまう人々の体の中では一体何が起こっているのだろうか? 脳内物質という言葉をご存知だろうか。脳内で分泌される神経伝達物質のことで、私たちの感情の変化なども、すべてこれらの物質の分泌による結果だと言われている。
ところで、「○○がやめられないメカニズム」は、脳内物質のバランスが崩れた状態だとする 説があるのだ。ストレス状態が長く続くと、興奮を抑える物質であるセトロニンという物質の量が少なくなってしまう。
一方で、ストレスを忘れようと一時的にアルコールなどを摂取すると、ドーパミンという物質が分泌される。これは、日常生活で気持ちいいと感じた時に脳内で分泌される神経伝達物質だ。つまり、興奮を抑える物質が少ない状態で、気持ちいいと感じる物質が分泌されてしまい、普通の人以上に気持ち良さを感じてしまうメカニズムが成立してしまうのである。そして、この状態がおさまると、再び気持ちよさを求めてアルコールに手を出してしまう。根源であるストレスが解消されない限り、これが繰り返されるのだ。
引用元:たばこ、酒がやめられないメカニズム
お酒やたばこがなかなかやめられないのは、ストレスに対する脳の働きが大きく影響しているんですね。
アルコール依存症になってしまうと、ますます止められなくなる
次に調べたのが、お酒がやめられない病気として有名な「アルコール依存症」です。この病気にも程度があって、自分の努力だけで改善できる程度「常用量依存」と、医者や周りの助けなしには改善が見込めない程度「強迫飲酒」さらに「連続飲酒」があります。
一段階ずつ進んでいくアルコール依存
アルコール依存症の症状は少しずつ進展する
最初は「機会飲酒」で、宴会などがあるときだけ飲むという状態で、それが大きな問題になることはほとんどない。
しかし、機会飲酒をくり返していると、やがてそれが「習慣飲酒」となり、毎日飲む習慣ができてくる。ごく普通のビジネスマンにも多いと思うが、アルコール依存としては「常用量依存」に分類される。人によって差はあるが、健康上の問題が出てくる。酒を飲むことで肝臓やすい臓に障害をもたらしたり、逆流性食道炎、糖尿病や高血圧を悪化させる場合もある。各種がんなど、飲酒によってリスクが高まる病気は多い。
さらに依存が進むと「強迫飲酒」の段階となり、飲む時間と場所のTPOをわきまえなくなる。翌朝、運転しなければいけないのに、酒が残る時間まで飲んでしまう。朝、キオスクでつい缶チューハイを飲んでしまう。こうなると医療機関でもアルコール依存症と診断される。状態が悪化すると、仕事の欠勤などを重ねて、同僚や家族から「絶対飲むな」と詰め寄られても、隠れて飲んでしまうようになり、仕事の問題、経済問題も抱えるようになる。
アルコール依存症の最終段階が「連続飲酒」だ。垣渕医師は「起きている間は飲み続け、1週間もすれば体が耐えきれなくなり、医療機関に入院することになる」と話す。連続飲酒の段階まで進むと、断酒治療によりアルコール依存から一度は回復しても、何かのきっかけでアルコールを口にすると、再び連続飲酒をくり返してしまうことがあるという。
引用元:お酒が…。「分かっちゃいるけど止められない」 コレってまさかアル中?
ある程度の期間を飲み続けると、止められなくなってしまい、どんどん階段を転げ落ちていく。”習慣飲酒”、”脅迫飲酒”から”連続飲酒”。それが依存症と言われる所以だとよくわかりました。
アルコールの脳に対する作用メカニズム
”アルコールは『出来損ないの麻酔薬』です”、くすりを飲むときと同じ態度で接しなさい。つまり”決められた量と回数を守りなさい”ということだと思いますが、わかりやすい表現だと思います。限度を超えると、薬が毒に化けてしまうということですね。
どうしてアルコール依存は進んでしまうのか。そこにはアルコールの脳に対する作用メカニズムが関与している。垣渕医師は「多くの患者さんは、アルコールは食品や嗜好品だと思っていますが、その性質を理解するには、アルコールは医薬品だと考えた方がいい。分かりやすくいえば、アルコールは『出来損ないの麻酔薬』です」と話す。
例えば、アルコールには脳内で興奮を起こすグルタミン酸などの神経伝達物質の働きを抑制する作用があり、飲むと不安が解消したり、リラックスした気分になったりする。さらにオピオイドという脳に快楽をもたらす神経伝達物質が分泌され、楽しい気分(多幸感)をもたらしてくれる。こうした作用が、仕事の疲れなどを癒してくれるほか、音楽家、建築家など芸術的なセンスを求められる仕事などでは、お酒が仕事にプラスに働くこともある。
しかし、こうした作用には、徐々に耐性ができる。つまり、脳はアルコールがある状態に順応してしまい、アルコールが消失すると以前より不安が増し、緊張が高まってしまう。それを解消しようと、飲酒の欲求が高まってくるのだ。
引用元:お酒が…。「分かっちゃいるけど止められない」 コレってまさかアル中?
脳は糖分を求めるという話を聴いたことがあります。アルコールについても同じことなんですね。単に意識の持ちようだけの問題ではなさそう。
アルコールを抜こうとしたときに起こる症状が怖くてまた飲んでしまう
一旦アルコール依存症になってしまうと、やめた後に起こる幻覚症状が怖くなって、再び飲み始めてしまう。このあたりを解説した説明を引用します。
アルコール依存症が重くなると、せっかくお酒を断っても、しばらくすると幻覚や体の震えが出てしまう。お酒を飲むとぴたりと治まる。幻覚や体の震えなどが怖くてお酒を止められないということが起こります。これでは、一旦深みにハマると抜け出せなくなってしまいますね。
アルコール依存症になると、アルコールの影響下に置かれる時間が長くなり、それだけ脳の活動は長時間抑制されます。
このような状態の人が断酒すると、抑制効果に対抗していた神経の過剰活動(「退薬症状」)が現れ、不安感やいらつきが生じたり、吐き気や嘔吐、動悸や発汗、あるいは寝汗や不眠などといった症状が起こります。
これらは軽い場合の退薬症状ですが、退薬症状が重い場合、細かな文字を書くと手や指が震えたり(手指振戦)、てんかん発作と同じ、全身が硬直して意識を失う全身けいれん発作が起きたりします。
また、実際には目の前にいない小さな虫が多数見えたり(幻視)、そばにいない人の声が聞こえてきたり(幻聴)する「幻覚」症状や、さらには“振戦せん妄”と呼ばれる、“酔いから覚めて2、3日経って、全身に震えが起き、日時や場所を取り違え、幻覚(幻視や幻聴)で精神の異常興奮が起き、周りの制止も聞き入れない特殊な意識障害”が起こることもあります。
このように重い退薬症状が現れる状態を「身体依存」があると言います。
引用元:アルコール依存症の症状):引用元のページが削除されてなくなってしまいました。
アルコール依存症、本当に怖い。
まとめ
このようにネットで調べてみると、習慣化したお酒をやめるのがいかに大変かわかってきました。こうなれば開き直って、”脳が飲酒をやめさせまいとするんだから、お酒が簡単にやめられないのは当たり前”と受け止めなければなりません。そのうえで、断酒という課題に対処しなければなりません。
私は痛風発作の再発が怖いので、なんとかしてお酒はやめたい。このつぎは、お酒が体に及ぼす影響をもっと知って、断酒を始める決心を強めていきます。