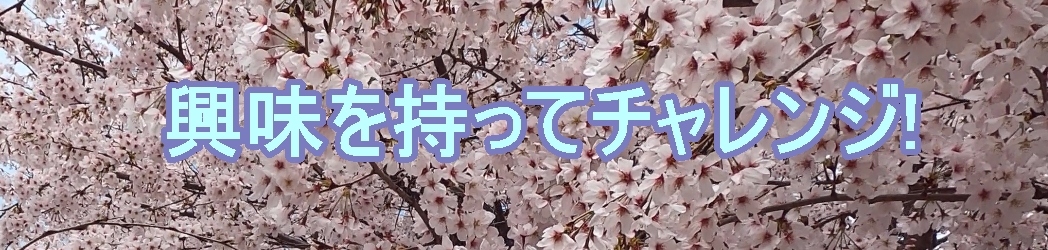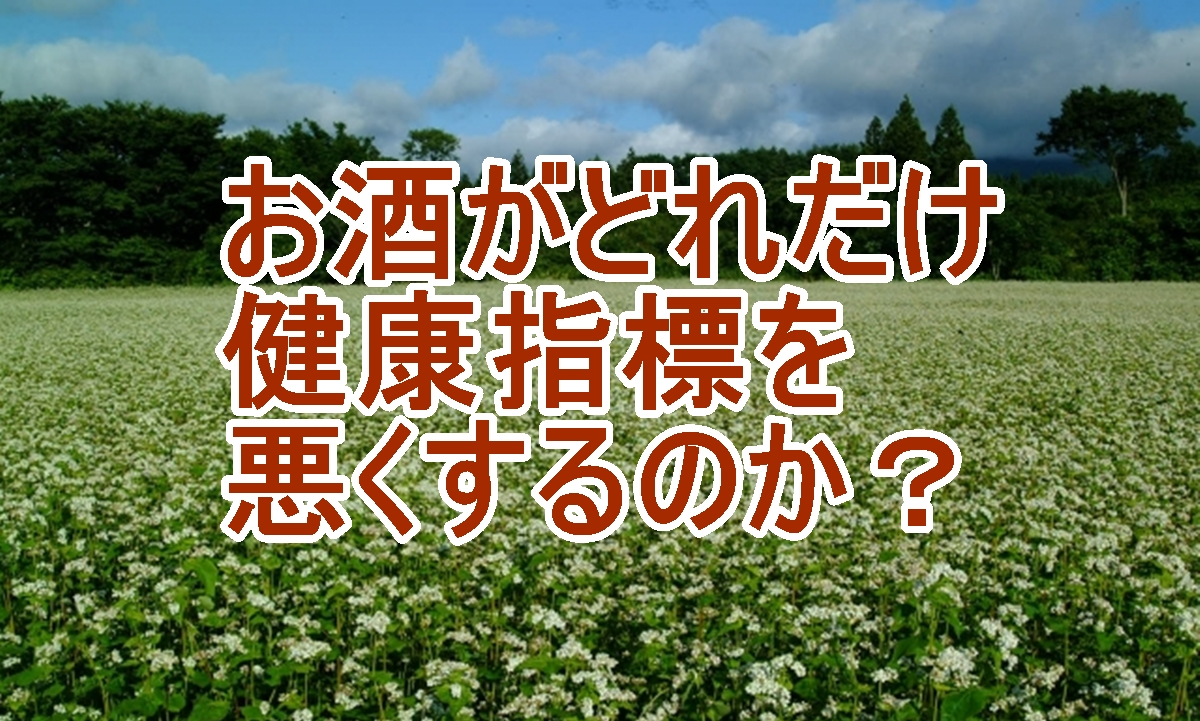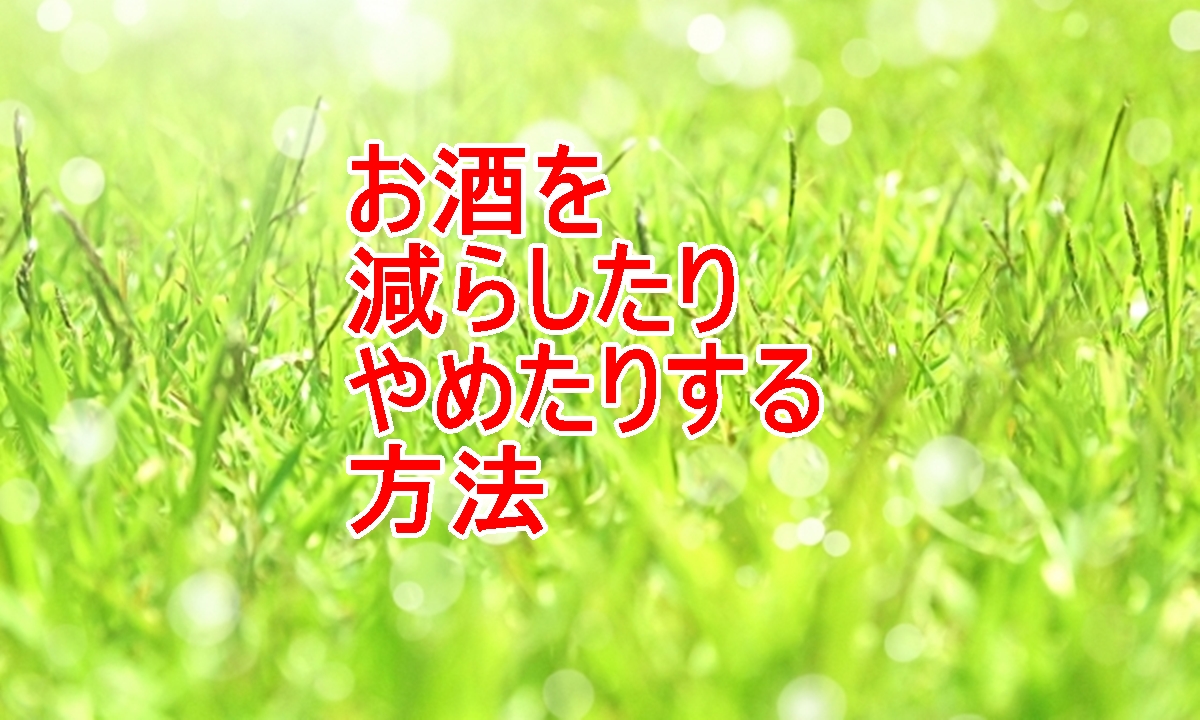はじめに:
お酒の飲み過ぎによる、尿酸値、血圧、中性脂肪などメタボリックシンドローム(メタボ)の代表的な指標への影響をネットで調べて、お酒が身体にどれだけの影響を与えるか知識を深めます。お酒を飲みすぎて起こる病気についての理解を深めます。お酒のリスクをしっかり自覚して断酒の決意を固めていきます。
お酒をやめるためには、自分の身体の問題として真剣に捉えられないと、真剣には取り組めません。前回は酒の飲み過ぎがどれだけ肝臓に悪いかでお酒が肝臓の代謝機能を大きく損ない、身体の栄養素を奪ってしまうことがわかりました。今回は、お酒が身体に与える影響を深掘りしていきます。前半はネットの情報を引用して様々な指標について、お酒(アルコール)との関係を理解します。後半はお酒が様々な病気を引き起こすことについて、わたしなりに理解した内容を紹介します。
酒とメタボの指標の関係
お酒(アルコール)の影響が身体の健康状態を示す指標にどのように現れてくるのかを、ネットで改めて検索してみました。長くなりますが、今後の私へのいましめのために要点を引用しておきます。
酒とメタボの指標の関係について調べる
尿酸、血圧、中性脂肪、高脂血症、糖尿病など気になるワードについてのアルコールとの関係を調べてみました。
尿酸(痛風)とアルコールの関係
アルコールが尿酸値を上昇させることについての解説です。アルコールが分解されるときに乳酸が作られ、乳酸が体内に尿酸を蓄積させることがわかります。
アルコール飲料を飲むと尿酸値は一時的に上がります。アルコールが体内で分解される時に尿酸が作られること、その際にできる乳酸が体内に尿酸を蓄積すること、一部のアルコール飲料には尿酸の元になるプリン体が多く含まれていることなどがその主な原因です。アルコールが代謝されるときに尿酸値が上がるので、どんな種類のお酒でも尿酸値や痛風にはよくありません。
引用元:尿酸値を上昇させる要因
血圧とアルコールの関係
アルコールを取り続けると血圧が高くなることがわかります。
飲酒により一時的に血圧が下がることもありますが、アルコールを継続して摂取すると血圧を上昇させます。また、節酒を続けると、わずか数日のうちに血圧が低下することもわかっています。高血圧を防ぐためにも、血圧の計測をしながらアルコールと上手に付き合っていきましょう。
日本酒1合で血圧が3mmHg上昇する
どのくらいのアルコール量で血圧がどの程度上がるのかご存じでしょうか?
引用元:高血圧の原因(3)飲酒(アルコール) ヘルスケア大学(引用元がリンク切れ)
アルコールを30ml摂取すると、血圧は3mmHgも上がるとされています。30 mlと言うと、日本酒では1合、ビールは大瓶1本、ウイスキー(シングル)やワインだと2杯分に相当します。このように、意外と少ないアルコール量で血圧が上がってしまうのです。
血圧を上げないための飲酒の適量として、男性で20~30 ml、女性の場合は10~20 mlと考えておきましょう。
中性脂肪とアルコールの関係
アルコールを取り続けると、中性脂肪が蓄積されることがわかります。
アルコールを体内に取り入れると、肝臓に運ばれそこで分解・代謝され体外に出ていきます。体外に出ていくのなら問題ないのでは?と思うかもしれませんが、実はこの分解・代謝をする中で中性脂肪が合成されているのです。ここで作られた中性脂肪は丸1日くらいの時間をかけてゆっくり、各器官などに運ばれていきます。ですから、日常的にアルコールを過剰摂取してしまうと、肝臓への負担が大きくなり、アルコールの分解・代謝はもちろん、中性脂肪の運搬も滞ってしまうのです。
本来、アルコールは適度に摂取していれば、血行が良くなりますので健康に良い作用もある飲み物です。ですが、その摂取量やおつまみの摂り過ぎで、一転してアルコールが害になってしまうのです。
もしも、飲みたいだけ飲んで体のことを考えない日々を長く過ごしていたとしたら、かなりの確率で肝障害を引き起こすことになります。中性脂肪の蓄積も生活習慣病になる主要因ですから、若いから大丈夫だろう、自分は健康だから問題ないなんて思ってはいけません。休肝日を設けつつ、1回の摂取量にも気を配って、お酒と楽しく付き合っていきましょう!
引用元:中性脂肪を下げる(引用元がリンク切れ)
アルコールと高脂血症
以下の引用文はわかりにくく感じましたが、適度な飲酒であれば健康に良いが、過渡の飲酒がよくないことを説明してくれています。
血液中の脂質が基準値を超えてしまうことを高脂血症といいます。アルコールが関係する高脂血症は中性脂肪(トリグリセリド)とHDLコレステロールの増加です。飲酒時の摂取エネルギーを減少させれば基準値にもどる可能性もありますが、アルコールの代謝そのものに伴う脂質代謝異常もからんでいる場合は、飲酒コントロールを行うことも必要です。
血中トリグリセリドが増加する原因として、食事から摂取する脂肪過多だけではなく、肝臓で合成されるトリグリセリドの増加があげられます。常習飲酒者にみられる高トリグリセリド血症は飲酒時の脂肪摂取過多のほかに、この後者の原因が絡んだ血清トリグリセリドの増加が原因となります。
もうひとつ、アルコールにより代謝が影響をうける脂質はHDLコレステロールです。コレステロールの主成分は動脈硬化を促進するLDLコレステロール(悪玉コレステロール)と動脈硬化の予防に働くHDLコレステロール(善玉コレステロール)があります。HDLコレステロールはアルコール摂取量の増加に伴って増加します。適量の飲酒(男性で1日日本酒換算1合ぐらい)であれば、血圧を上げずにHDLコレステロールが増加するため、脳血管障害・虚血性心疾患の発生率を低下させるといわれています。これが「適度の飲酒が寿命を延ばす」と言われるようになった所以です。
しかし一方で常習飲酒は血圧の上昇をもたらし、飲酒中の摂取カロリーオーバーや夜間に高摂取されるカロリーバランス、前述したアルコールの影響などによって高トリグリセリド血症や肥満を引き起こす場合もあるため、「適度の飲酒」が却って生活習慣病を促進してしまう可能性もあります。
一日あたり男性は純アルコールで20g(日本酒換算1合程度)女性はその半量までが、厚労省の提唱する「節度ある適度な飲酒量」の目安とされています。
引用元:e-ヘルスネット
糖尿病とアルコールの関係
アルコールが食欲を増進させたり、利尿作用によって血液中の水分が減ることが、糖尿病やその悪化につながることがわかります。
少量のアルコールは血栓を溶かしたり、できにくくしたりする、ということですが、一方で度を越えた飲酒はどうなるのでしょうか?
当然、言うまでもなく、身体全体にとって、飲み過ぎはよくないですよね。糖尿病の大きな問題は、血液の流れが悪くなることにありますが、実はお酒の飲み過ぎは、そのことと深い関係があるんです。
血液の流れが悪くなる原因は色々とありますが、その一つは脱水症状です。脱水症状によって血液の粘着度が増して、ドロドロになっていくと、気を付けなければならない深刻な合併症が起こりやすい状態になります。アルコールの摂り過ぎは、正にこの脱水症状を引き起こすのです。
でも、お酒も水分ですから、それを大量に飲むと水分補給をしている事になり、脱水症状とは逆なんじゃないの?と考えがちですが、アルコールは、ご存知のように利尿作用が大変強く働きますよね。飲めば飲むほど、トイレに行きたくなりますよね。
その尿によって、体内の大量の水分が失われていきます。そうすると、血液はドロドロしてきて、流れが悪くなり、糖尿病の症状が悪化するということにつながっていきます。ですから、酔っ払って、そのまま寝てしまい、朝まで全く水分補給をしない、なんてことは大変危険なのです。
さらに、アルコールは食欲を増進させる働きがあります。これはよく言われる点ですよね。食前酒などを利用される方が多いのもそのためですね。でも、言うまでもなく食欲の増進は糖尿病と闘っておられる方にとっては、大問題です。増進しては困るからです。いつもは食事制限で頑張っていても、お酒を飲むと食欲が増し、ついつい食べ過ぎてしまうということはよくある話です。これではせっかくの日頃の節制が台無しです。自制ができないなら、始めから止めておくのが賢明ですね。
引用元:糖尿病講座 流れて良くなる.com
メタボの指標についての私の実感
アルコール(酒)は尿酸・血圧・中性脂肪、高脂血症、そして糖尿病と強い関連性があることがわかりました。
これらの指標は私の現状を考慮するのに必要なものばかりです。つまみを食べずに飲んでいるからなのか、糖尿病の方向には行きませんでしたが、どろどろの血液が頭に浮かびます。血液が体中を巡って身体の維持・健康に重要な働きをしているのは間違いありません。これからはメタボの指標を良くしていきたい思いが強まります。
お酒の飲みすぎでなってしまう病気
アルコールとメタボの指標との関連について調べましたが、さらに病名をキーワードにしてさらに調査を続けます。
お酒の飲みすぎを続けると、重大な病気を引き起こしてしまいます。アルコールの影響をいろいろな病名の観点でまとめます。いちいち引用元は上げませんが、内容は一般的に流布している内容だと思います。
肝障害
アルコールは体内に入ると肝臓で分解される仕組みになっています。
つまり、体内に入ってきたアルコールの量が多ければ多いほど、肝臓の仕事はハードになるというわけです。
肝臓が分解し切れないほどの量のアルコールが入ってきたら、一体どうなるでしょう。アルコール性脂肪肝などのアルコール性障害が起こり、重症化するとアルコール性肝硬変に至る場合もあるのです。
肝硬変は肝臓が小さく硬くなり、肝臓としての機能を果たさなくなってしまう病気です。初期の自覚症状がほとんどないため早期発見されにくく、最悪の場合は命に関わることもあります。
癌
お酒と癌は切っても切れない関係です。
アルコールは口腔や咽頭、喉頭、食道、肝臓、大腸の癌の発生リスクを高める可能性が高く、お酒を飲まない人に比べて死亡率も高いことが明らかになっています。
さらに喫煙者となるとさらに癌発症率を高めることになりますので、健康的にお酒を飲みたいのであれば、タバコをやめてお酒は適量にとどめ、週に2日は休肝日を作るようにしてください。
もちろん禁酒することで発症率は確実に下げることが可能ですので、それが一番です。
高血圧
飲酒は一時的に血圧を下げると言われていますが、長期的に飲酒を続けることは結果的に血圧を上昇させることにつながるということが分かっています。
もちろん飲酒の際のおつまみが高血圧の原因になっていることも考えられますが、お酒を飲まない人に比べて飲む人の方が高血圧の割合が高いのは確かです。
医者から高血圧を指摘された場合は、出来るだけ早く禁酒することをおすすめします。
依存症
アルコール依存症は本当に恐ろしい病気です。
飲酒量を自分でコントロール出来なくなり、ときには人格まで変えてしまうことになるのです。アルコール依存症の治療には長い年月を必要とし、周囲にも大きなダメージを与えます。依存症にならないためにも、早めに禁酒を決意してください。
精神的疾患
お酒を飲むとぐっすり眠れるようになる、と思っている人も多いようですが、飲酒は睡眠の質を悪くするのが現実です。
不眠からうつ病などの精神的疾患を発病する人も少なくありません。
お酒は適量であればストレスを解消してくれますが、それを超えると精神をも蝕む可能性があるものだということを忘れないでください。
(引用元:お酒による害を知れば禁酒は100%成功する!)(引用元がリンク切れ)
調査した内容を自分に当てはめる
以上で挙げたアルコールの飲み過ぎで掛かる病気は、すでに広く知られている内容かと思いますが、再確認できました。わたしに当てはめてみます。
- 肝臓の働きを示す指標のうち、γ-GTPが非常に高い状態が続いていたうえに、他の指標(ASTやALT)も悪くなりだしました。いよいよ肝臓がギブアップしだしたか?
- タバコはずいぶん前にやめているので当面は癌の心配は少ない?
- 高血圧は当てはまります。上も下も値が高い状態。
- 依存症、はっきり言ってこの1年の状況は依存症になってました。精神的疾患で自分の人格が保てなくなるなんて、恐怖です。
アルコールを断つ決意
いろいろと調べて、私に当てはまることが多くて嫌になります。
お酒が自分には有益にならないことが、はっきり自覚できました。
関連記事
お酒をやめる決心をようやく固められました。次は、お酒を控えるとか、やめる方法とか、どうしたら本当にやめられるかなどを調べて実践します。